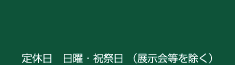茶の湯で使われるようになった花入の始まりは仏器としての花器であったと考えられます。いわゆる三具足や五具足の花入です。
茶の湯で使われるようになった花入の始まりは仏器としての花器であったと考えられます。いわゆる三具足や五具足の花入です。
「押板」に「本尊」を掛け供える物として花を入れ多くは一双の物で「唐銅花入」または「青磁」などが鎌倉時代から移入されていきます。
茶の湯では唐銅、胡銅と呼ばれる花入は原料名、金属名としては「ブロンズ(青銅)」にあたります、その始まりは古く中国の「夏」や「殷」「周」時代の「青銅器」が始まりです。
当時は神に捧げる酒器の様な物だったようですが後世になって花器として使われ出したようです。やがて青銅器は殷代をピークとして漢の後期には著しく衰退するようになります。
かわってこの頃から焼かれ始める「青磁花入」は、唐代には「秘色(ひそく)青磁」が完成しますが花入に昇華するには若干の時間を要するようです。
やがて「宋」の時代に入ると青銅器の形状、雰囲気を目指した青磁が現れ(砧、天竜寺、七官など)元、明時代までつづき茶道で使われる花入の全盛時代を迎える事となります。
室町時代にこれらの花入は「唐物」として茶の湯と共に我が国に招来する事となります。いわばこの頃の時代までに日本へ伝来した唐物花入を「真」の扱いをする花入に当たります。
一方、元のころ大成する「染付」「赤絵」は明代に盛んになりますが花入として日本への輸入が盛んになるのは江戸に入って「古染付」や「祥瑞」「呉須赤絵」と呼ばれる一群の茶道具としての注文品の輸入が始まってからの様です。
 その他「高麗青磁」「交趾」「安南」や「オランダ」など唐物に準ずる物として同じ扱いをすると良いようです。
その他「高麗青磁」「交趾」「安南」や「オランダ」など唐物に準ずる物として同じ扱いをすると良いようです。
唐物の中でも「釣船」の花入は一格落して「行」の格として扱うようです。
「七宝」「モール」の花入も「真」の部類ですがいささか軽めといってよいでしょう。