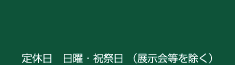和物の籠の花入はやはり利休の見立てによるもので漁師の持つ「魚篭(びく)」からヒントを得た「桂籠」などは赤穂浪士の討入にも登場する程有名になりました。
唐物の籠花入はその品格から自ずと事なるものとなります。大方、和物籠花入は風炉の時期だけですが唐物は炉の時期であってもまた「草」の花入れではありますが書院にもふさわしい花入として扱う事も有ります。
「草」の花入の代表としてはやはり竹の花入でしょう。
 利休の師、紹鴎がすでに「洞切」という竹の花入は創作していましたが、利休晩年小田原攻めの折秀吉に随行し韮山の竹をもって一晩のうちに三本の花入を削りその一本を秀吉に献上したところ秀吉はいたく不機嫌にその花入を庭へ投げ捨て花入にひびが入ってしまった、という利休と秀吉の美観の差が現れ初め亀裂が生じ始めたころの逸話がありますが、秀吉にえらく不評を買った竹の花入ですが、利休は死までの一年間にも多くの竹の花入を切っていますし後世多くの茶人も花入を切っています。
利休の師、紹鴎がすでに「洞切」という竹の花入は創作していましたが、利休晩年小田原攻めの折秀吉に随行し韮山の竹をもって一晩のうちに三本の花入を削りその一本を秀吉に献上したところ秀吉はいたく不機嫌にその花入を庭へ投げ捨て花入にひびが入ってしまった、という利休と秀吉の美観の差が現れ初め亀裂が生じ始めたころの逸話がありますが、秀吉にえらく不評を買った竹の花入ですが、利休は死までの一年間にも多くの竹の花入を切っていますし後世多くの茶人も花入を切っています。
これまでの花入と異なる点は「作り手が茶人」に移ったという点だと思います。茶人という工芸の素人が作り得る品物が一種の芸術品となった訳ですから秀吉が気に入らないのも尤もなことではあります。これは誰もがなし得たことではなく「利休」という侘び茶の大成者でなければ野にある竹を花入にしたものを何人も認めえなかったと思います。
最初の掛け物のときも書きましたが竹の花入も同じ様に「人格」を見出すための道具ですから職人が作ったものと異なる格調を備えた物なのです。お人が現れていなければ竹の花入としての意味はありません。
書き遅れましたが先程の利休韮山の三本の花入にはそれぞれ「圓城寺(おんじょうじ)」「よなが」「尺八」と銘が付いています、その誕生のときから竹の花入は「銘」とは切り離せないものなのですから。