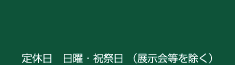(天目茶碗)
中国十世紀の北宋時代、福建省出身文化人官僚「蔡襄」が一〇五一年に著した「茶録」により「天目」が注目され、茶の色を引き立てるに適した釉色として、流行し「青磁、白磁」を圧倒していきます。
主な産地として福建省で焼かれた物を総称して「建窯」と呼び「建盞天目」といもいいます。この中には国宝「稲葉天目」を代表とする「耀変天目」があり南方録の記述にある伝説の「花山(かざん)天目」も耀変天目とされています。ほか「油滴天目」「兎毫盞」とも呼ばれる「禾天目」また、生産時にはむしろ下手と見られていた「灰被天目」等があります。
もう一方の生産地である「吉州窯」にはその模様が鼈甲の様だという事から「玳皮盞(たいひさん)」別名「鼈盞(べっさん、玳皮は鼈甲のこと)】や見込みに木の葉を焼き付けた「木の葉天目」日本には伝来のない「鷓鴣斑(しやこはん)」等があり宋代王朝の栄華を思わせます。ここでいう天目茶碗を表す「盞」は茶碗のこと、と思っていただいて結構ですが、「天目茶碗」にしか使わないと心得ておくと良いでしょう。また「七種天目」として「無理矢理覚えた」ことのある方もあるかと思いますが、例の数字の語呂合わせ、今の分類とは異なる面もあります。
鎌倉、室町時代には、その一部が「喫茶法」と共に我が国にも輸入され永く茶を飲むための器として上流社会で愛用されるようになり、当時の「唐物趣味」とあいまって、「台子書院の茶」には欠かせないものとなります。現在でも古式茶法の習い事としての「台天目」や「台子」の点前には必ず(写でも)使用されていることでも分かる事と思います。やがて北宋の喫茶法である「抹茶法」と共に中原から周辺諸国へ伝播して各地にその名残をとどめて行きます。
(天目台)
これら「天目」または「青磁茶碗」を扱うのに前述した「托」すなわち「天目台」に載せて用いました。しかし不思議なことに現存する「天目台」のほとんどは「明」時代の物であり、現在稽古用に用いられる真っ黒け(真塗)だけが「天目台」ではなくむしろ「堆朱」「堆黒」「紅華緑葉」「屈輪」「螺鈿」と実に様々な装飾が用いられ伝物としての華やかさを感じさせる物です。ただし最も「信」として用いるべき天目台は「尼崎台」と呼ばれる「唐物真塗覆輪添」の台であり近年では南宋時代のもであるとわかり、最も格式高く用いるべき物です。
(瀬戸天目)
茶の湯、当時は闘茶や寺院での儀式などに茶の湯が盛んに用いられるようになると唐物天目茶碗の代用品として登場した「瀬戸天目」は寺院の「数茶碗」として「天目盆」と呼ばれる大きな盆に載せられ使われていました。
これら一部和物の「瀬戸天目」を含め「第一期唐物茶碗」とも言える茶碗群は利休による詫び茶の流行と共に急激に衰微していきます。山上宗二記その当時の流行を伝え「唐物廃りたり」としています。唯一例外は「珠光青磁」と呼ばれる、本来青磁としては失敗作、下手物とも言える黄色がかった緑色の茶碗でした。これは「侘茶」に向く物として天目台には載せず使われた物と思われます。これ以降、遠州時代に「古染付」「祥瑞」「安南」などが注目されるまで、暫く茶の湯の世界から遠ざかります。
(天目、青磁茶益の用い方)
これら「第一期唐物茶碗群」殊に「伝世」の物は文化財として貴重であることもあり実際に茶会、茶事に用いるには重苦しく、使いにくい物です。また近年中国国内で窯跡から大量の「建羞天目」が掘り出され流通しています。本物(伝世ではなく発掘)であっても、写であっても「天目」「青磁茶碗」は「伝物の稽古」にこそ相応しい物と心得る方がよいでしょう。