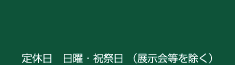茶碗3(国焼茶碗、ほか)
美濃・瀬戸茶碗
「瀬戸天目」から始まる「瀬戸焼」「美濃窯」の茶碗が「桃山茶陶」の代表へと変化していくのは「黒樂茶碗」に先行先行する「瀬戸黒茶碗」から始まる、とも考えられます。
「引出し黒】と呼ばれる技法は鉄分を含んだ釉薬をかけた焼成中の茶碗を窯の中から引き抜き急激に冷却することによって深い黒色を醸し出す技法で、「瀬戸黒茶碗」以前に存在しなかった高台が低く、横からのシルエットが四角、半筒茶益といって良いほどの角張った腰など特異な形状をしています。
「瀬戸黒茶碗」やその後にあらわれる「志野茶碗」はそれまで主流として用いられてきた「天目茶碗」や「井戸茶碗」のような「杉形(すぎなり)」や利休が手がけ始めていた「長次郎茶碗」のような「碗形(わんなり)」でもない独自の形態はとこから来たのでしょうか,
これは瀬戸、美濃の作家が戦国時代末期の桃山という時代を茶碗という世界で発揮した表れの一つとも思われます。まったく日本という国土の生み出した陶器の形態の一つではなかったのではないでしょうか。
「黄瀬戸」と呼ばれる一群の焼き物は「青磁」を目指した陶器といわれていますが「黄瀬戸茶碗」の多くは「向付」など食器を後の世に茶碗として見立てて使用した物がほとんどで、近世「写の黄瀬戸茶碗」もこれを襲っており、軽みのある使い方が似合います。
ただし 茶碗として作られた黄瀬戸が全くないわけではなく利休の師「北向道陳(きたむきどうちん)」の所持とされる「黄瀬戸茶碗」と「朝比奈」という銘を持つ茶碗があります。
のちに現れる「伯庵」という茶碗は「黄瀬戸の流れを汲む」ともいわれ、よく似た黄釉が特徴です。これは江戸幕府の医師「曽谷伯庵」所持の「伯庵茶碗」を本歌とする一群で「碗形の形状」をしており、現在では焼成地は「唐津」とも「朝鮮系」ともいわれています。
「瀬戸黒」を引き継ぐ形で登場するのが「志野茶碗」といえます。「日本の白磁、染付」を目指したとも言われる「志野焼」はそれまで出し得なかった「白釉」を「長石」と呼ばれる鉱石を砕いて作り「鬼板」と呼ばれる鉄釉によって単純な絵が描かれ作り出されたもので、茶人の間で盛んに使用されるようになります。
なぜ志野茶碗は人気があるのでしょうか。たとえば「国宝志野茶碗 卯の花垣」は江戸時代になって片桐石州公が内箱の裏に「やまさとのうのはな かきのなかつみちゆきふみわけし ここちこそすれ」と和歌色紙が貼られ、銘碗として志野茶碗中の最高峰とされています。
作られた頃は志野茶碗の草創期、やがて「桃山茶陶」の本領というべき「躍動した」茶碗へ変化していきます。また、白黒の逆転した「鼠志野」「練り込み志野」等も登場し当時「ひょうげたる」とも称される茶碗群が発展するもととなります。
どうやら、この躍動した茶陶の最盛期は十年ほどと考えられ「貴重な陶器」であり、広く欧米にまでファンもあり「桃山陶器」を代表して高い評価を受けているからなのではないかと思います。
躍動感のある変形した形状を主流とする傾向は時代が下がるに従い顕著になります。
これには「古田織部」の登場によるものと考えれられています。
瀬戸黒の技法を躍動した形状へ作り上げた「織部黒」はやがて志野焼の白地に鉄釉で絵を描く技法をその一部分に盛り込み「黒織部茶碗」となり、銅の発色を使いその代名詞とも言える「縁釉」を使った「織部茶碗」となっていきます。これは織部の創造による「利休へのアンチテーゼ」ともいわれ、穏やかな「長次郎」に対して大胆で踊るような造形は桃山期から江戸初期にかけて俄然注目されていきます。
食器の多い「黄瀬戸」を除き「瀬戸黒」や「織部黒」「黒織部」がほとんど茶碗の域を出ないのに対し「志野」は「向付」「鉢」など懐石の道具も多く「緑釉の織部」はこれに加え「燭台」「硯」「煙管」「敷瓦」にまで及びます。
高麗系国焼茶碗
萩、唐津、高取、その他の窯
秀吉の朝鮮出兵は朝鮮茶益の獲得も目的の一つだったとも云われ、「文禄、慶長の役」が国焼施釉を発展させたともいえます。現に半島の陶工が多く日本へ移植し、朝鮮半島内の堂記ががそれ以降ほとんど途絶えてしまうほどといわれるようになりました。
来日した陶工たちは各地に分散し「萩焼」や「唐津焼」「薩摩焼」などの九州諸窯の開窯や発展に深く関わるようになります。
殊に朝鮮半島の「土」と「釉薬」と「技術」で焼かれた茶扱は「火斗(ひばかり、火だけが日本の物と云う意味)」や文禄慶長の役以前に唐津で焼かれた「奥高麗」と云った茶碗は朝鮮の茶碗と同じ様にに用いられることもありました。
「萩焼」の祖「李勺光(りしやっこう)」「李敬」兄弟から始まる「萩焼」は萩焼城下
で十七世紀初頭に開窯された「松本焼」と呼ばれた「藩窯」に始まり「李敬」直系の「坂(高麗左衛門)家」と「三輪(休雪)家」の二家松本の地で、また藩の政策によって分窯した「深川(ふかわ)」では「坂倉(新兵衛)家」「田原(陶兵衛)家」「坂田(泥華)家」の「深川御三家」がおのおの連綿と伝統を守っています。
朝鮮陶器をルーツとする萩焼茶茶碗も藩主の毛利家が古田織部とも親交があり大きな影響を受けたとされます。
また、三輪(休雪)家」は再三に亘り京へ赴き「楽焼」の修行をし、萩焼茶碗は徐々に「和風化」していきます。江戸前期では、大名間、或いは萩藩上流武士層用の「贈答用」として完全なる「統制品」であり、殊に「濃茶用」として焼かれた大振りの茶碗は度々禁令が出るほどの人気を得、やがて本家の「御本茶碗」を駆逐するほどになります。
一般にまことしやかに伝えられる萩焼の切高台は「庶民」用「殿様」用には切高台でない物、という区別はまったくの俗説であり、度々の禁令にも関わらず「ご禁制」の茶碗が出回るようになる幕末まで「庶民」はおろか「大商人」でもおいそれとは手にすることはなっかたというのが実状ではないでしょうか。
ですから殊に「千家に関わる萩焼茶碗」は江戸時代には楽茶碗に比して誠に少なく「不審庵伝来、武蔵野」「了々斎書防、雪獅子」などが知られる位ではないでしょうか。
「坂高麗左衛門」の弟子で深川焼の陶工であった「倉崎権兵衛」は隣藩、出雲(島根)の「松江藩松平家」に請われ「楽山焼(出雲焼)」の祖となり現在に続いています。
「萩焼」はその人気を表す言葉に「一井戸、二萩、三唐津」とか「一楽、二萩、三唐津」と言った言い廻しがあり、前者が先に謂われだし、後者が千家筋による解釈か、とも言われています。 ’
「唐津焼」も朝鮮半島の技法を導入したとされていますがその開窯は「文禄、慶長の役」】よりも古く千五百八十年頃と考えられるようになってきました。
唐津焼で初期の代表的な茶碗の一つ「奥高麗茶碗、子(ね)のこ餅」は利休が所持していた
ことでも知られています。茶碗では前述の「奥高麗」をはじめ「絵唐津」「朝鮮唐津」「斑唐津」「瀬戸唐津」等がありますが「奥高麗}を除けば「濃茶茶碗」には向きにくい物が多いようです。
古田織部のエネルギーは九州の地でも大いに発揮され、桃山陶器として慶長年間には遠く京都などに盛んに送られていますので「織部、志野」など「美濃瀬戸系陶器」や地元京都の「楽焼系陶器」と共に、京都市内の地中から数多く発掘されています。
また窯場も「唐津藩」そのものは今の佐賀県にありますが、隣県長崎・福岡に亘る広い範囲でいわゆる「唐津焼」の窯場があり、周辺には「高取焼」や「上野焼」「小岱焼」など類似の陶
器が九州北部を中心に点在し焼かれていきます。やがて「伊万里焼」の登場により急激にその人気と技術が衰えていき、茶碗の存在は唐津同様十七世紀半ばまでに見られるだけのようです。現在その道統を伝えるのは、唐津藩お抱えの「中里(太郎右衛門)家」があります。
小堀遠州の茶陶
古田織部の没後、次の時代を担う大名茶人「小堀遠州」が茶の湯の世界をリードしていきます。
そして、茶人が茶道具、茶法、茶室などを創造し新しい茶道を生み出していった最後の世代といっても過言ではないと思います。
利休の生み出した「楽茶碗」織部の時代には「志野」「織部」「美濃伊賀」「伊賀」「信楽」その影響下にあった、「唐津」「萩焼」遠く朝鮮半島の「御所丸」など それまでにない茶道具を生み出していきましたが、「遠州」はそれを引き継ぐ形として、「遠州伊賀、遠州信楽」と称される一群もあり、その影響を残しています。
朝鮮半島には「御本」と呼ばれる新たな高麗物を創造して行きます。時代は幕藩体制が安定していこうとする時代です。
織部の没年である1615年は徳川幕府の基本法である「武家諸法度」が制定され、桃山時代とと遠う価値観が芽生えはじめ遠州の茶道具は「武家社会」に見合う道具として見出されたと言っても良いでしょう。
「文禄、慶長の役」によって朝鮮半島からの陶工が移入し九州の地には「細川三斎」が「上野焼」を始め、また隣接する「高取焼」は黒田長政の開窯とされますが、寛永時代、遠州の指導により「遠州高取」と呼ばれる現在につながる高取焼を作り出し、「上野焼」にも影響を及ぼしていったとされていますし「唐津焼」にも少なからず、変化をもたらしていき「綺麗寂」と呼ばれる「茶陶」を開花させていきます。
十五世紀中頃瀬戸焼を原点とする遠江の「志戸呂(しとろ)焼」。江戸初期の開窯とされる宇治焼とも呼ばれる「朝日焼」や近江の「膳所(ぜぜ)焼」も遠州の影響が考えられています。また奈良の「赤膚(あかはだ)焼」は遠州の「印」を使用しているものの「茶陶」と呼べるものは当時はなかったようですが、必ずしも遠州の指導を受けた物ではない「古曾部(こそべ)焼」を含め「遠州七窯」と呼ばれるようにまでなっていきます。
高取焼の茶碗「面取」や「朝日焼」「膳所焼」江戸後期に登場する「古曾部」を除けば茶碗としては数も少なく、陶質としては茶碗に向かない焼物と言っても良いかもしれません。
濃茶には向かない、「第二期唐物茶扱」
「遠州」の登場により江戸初期からは中国、元時代に根源を持つ「青華」を茶陶としての「古染付」「祥瑞」「呉須」として昇華させていきます。
一般の「茶碗」や「陶磁器」の解説書では「天目」や「青磁」の茶扱と一緒に分類、解説されることが多い「古染付」や「祥瑞」は江戸時代になって日本から、おそらく「遠州」によって中国へ発注したと言われています。その後も、陶工を遣って、その技法を日本へ移入したとも云われるぐらいです。
時代はむしろさかのぼりますが、十四から十五世紀のベトナム産「安南」はやはり茶碗であったのではないかと言われるようになっています。利休、織部時代にも「染付」自体は存在していましたが茶の湯に取り入れられることはありませんでした。
武家茶道が確立する新時代の茶陶と位置づけられたのでしょうか。この頃から日本へ輸入され使われるようになります。
江戸時代の日本では「絵高麗」という名を冠することになった中国「磁州窯」産の「絵高麗梅鉢茶碗」は同じように江戸時代には「絵高麗」と呼ばれる朝鮮陶磁の「鶏龍山」の茶碗と同類と分類されていました。
準唐物の扱いと考えられる「交趾焼」とは「コーチンチャイナ」即ち「唐三彩」の流れを汲み「香合」を代表とする「交趾焼」を元に「永楽和全」が開発したとも言える「国産品」で「海外産」の茶碗はありません。
東洋の陶磁器の模倣から始まる欧州陶器を取り入れた「和蘭」物も茶碗に関しては極僅かです。
いずれにしてもこの第二期唐物茶益群と呼べる茶碗群は基本的には濃茶に向かないと思います。
「京焼」の世界
遠州と少し立場を異にしますが同じ時代仁「綺麗寂」を求めた「金森宗和」の指導で作られた「仁清焼」は京都洛西、御室仁和寺で焼いたこと仁より「御室焼」「仁和寺焼」とも称されました。作者である色絵の完成者「野々村清右衛門(仁和寺の清右衛門から仁清)」の「仁清焼」は「信楽の土」を用い特徴である「長石」を水で溶き、取り除くことによって真っ白い胎土を手に入れることで「色絵」と言われる「上絵付技法」を完成させます。
「仁清焼」の登場は茶陶の世界に「絵画」を持ち込み茶の湯で重要な要素となっていく「季節感」を鮮明に打ち出すことも可能になっていきました。
元禄時代を代表する芸術家「尾形光琳」を兄に持つ「尾形乾山」は仁清の手ほどきを受けた人物で樂家五代になる「宗入」は従兄弟という恵まれた条件の下、兄光琳の絵付けによって絵特の陶器を制作していきます。
京都では次々と新しい茶を表現するための茶陶が焼かれて行きます。そして、これらの焼き物に共通する特徴は「茶人の注文」仁依っている点です。
殊に「仁清」の品物はその印象から「公家」社会からの注文が多いと考えられていましたが、むしろ「武家」からの注文が多くあったと言われています。
これらの陶器は、やがて「京焼」とも称されるようになていきます。
仁清に先行する「粟田口(あわたぐち)」は「茶入窯」から仁清の影響を受け「色絵物」へ変化していきます。
続く「御菩薩池(みぞろがいけ)」「黒谷」「押小路」等と共仁「古清水」と称されていき洛中洛外へ分散発展していきます。
そんな中、十七世紀中葉仁九州の「有田焼磁器」が流入をきっかけ仁「京磁器」の開発が望まれます。やがて十八世紀末に「奥田頴川」が釉の縮れ、釉はげが特徴の「赤絵磁器」を作っていきます。
頴川と同門といわれる「清水六兵衛」はその名の示すとおり「清水焼」の代表的作品を作り出し、頴川門下の「青木木米」は煎茶器仁も浸出、和風化を進める初代「高橋道八」二代「仁阿弥道八」は乾山風、仁清風、楽焼までこなす上手です。
「永楽保全」は土風炉師「西村善五郎」家の第十一代継承者です。
紀州徳川家御庭焼、偕楽園へ参加、藩主徳川治宝(はるとみ)公から「河濱支流」の金印と陶号として「永楽」の銀印を拝領し、「永楽保全」を名乗ります。
出入りの「千家」「三井家」の茶陶名品の写から「染付」「交趾」「金欄手」などを極めていき独白の発展をさせ、茶陶としての完成度を高めます。
彼らは文化文政時代の京文化爛熟期の代表作家たちでしょうし「清水六兵衛」「高橋道八」「永楽善五郎」の各家は明治維新や先の大戦の動乱をくぐり抜け今なお連綿と京焼茶陶の伝統を守り続けています。
「焼き締め陶器」の茶碗
国焼の最古参である「備前、信楽物」を代表とする「日本六古窯」など「侘びの陶器である焼締陶器」は、茶碗として使用するには難しいものです。
まして濃茶の茶碗には向かない物と言って過言ではないでしょう。
その焼締まりすぎた触感はあまり茶を飲むには適しませんし取り合わせでは「水指」や「花入」の方が似つかねしい陶器です。
茶の湯に「絶対」はないのですが、「しないほうがよい」や「こっちのほうが良い」と言うことはあります。勿論これらの「焼き締め陶器」の信楽焼「花橘」同じく「水の子」など「名物茶碗」が無いわけではありませんが、優先的に茶碗としてもとめる必要は無い物の一つです。
「備前焼」に至っては伝世品はないといっても良いほどです。
藩窯、
島津藩には「薩摩焼」隣の長崎県諌早家の「現川焼」紀州徳川家の「偕楽園焼」岡山藩筆頭家老、伊木三猿斎の「虫明焼」松平不昧の「楽山焼」「布志名(ふじな)焼」大和郡山藩主、柳澤吉保の孫、柳澤尭山の「赤膚焼」幕府大老、彦根藩、井伊直弼の「湖東焼」「賀集眠平、淡路焼」など大名や藩が育てた茶陶窯が、江戸時代中葉から後半にかけて次々と藩窯として築かれ発展していきます。
「伊万里」「九谷」に茶碗なし。
江戸時代初期、ヨーロッパで人気を博した東洋陶器の最先端は「景徳鎖」を離れ九州鍋島藩藩窯、有田で焼かれたいわゆる「伊万里焼」の磁器でした。後に京焼に影響を及ぼす事になりますが、ついぞこの地で茶の湯の茶陶が焼かれる事はありませんでした。