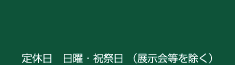点前の道具でやはり第一に上げなければならないのは「茶入」でありましょう。入門し徐々にお稽古が進み「濃茶」の点前な入ると少し成長した気になりませんでしたか。また、いろいろなお点前になれ、段々に進むと「今日からは唐物のお稽古を致しましょう」とか「そろそろお台子にはいりましょう」とか師匠にいわれドギマギした経験はだれでも持っているのではないでしょうか。
そういった「伝物のお点前」は複雑になりますし、とても丁寧になります、おまけに盆に載る点前まで出てきてどうしようかと思ったりした事も有ったのではないでしょうか。たかだかお茶を入れる器に過ぎないのに何故こんなにまでして扱わなければならない茶道具があるのかと思いませんでしたか。そこで何故そうなるのかと師匠に問うと、「これはこの茶入が「唐物」といわれる物で昔々、支那から渡ってきた茶道具で、なお且つ昔は領地一国と取り替えたほど貴重な物まであった」などという説明に、「そうすると貴重なものでおまけに高そうな物なんだなぁ。」と一応納得してしまったりします。
しかしお稽古の道具となると点前は異なるにも関わらず「和物」から「唐物」、「台子」に至るまで「使う茶入」が同じだし、はっきりいって「どこが違うのかなぁ?」と思われることはなかったでしょうか。
そもそも室町時代においては抹茶になる前の葉茶「碾茶」を入れる「茶壷」の方を第一の道具と考え「大壷」と称し、対する「茶入」は「小壷」といって区別していました。時代によりこちらの方が重要に扱われるようになります。
ところで「唐物茶入」とは何物?という疑いを(疑問でなく)持たったことはないでしょうか。実際、一口に「唐物茶入」といってもピンからキリ迄、といったら少し言い過ではありますが、まぁいろいろある上に現在に至るまで支那大陸の何処で焼かれた物なのかは未だに不明だということですし、(最近一部が発掘され徐々に唐物茶入の研究は進みつつありますが)此で、ハテ?とお考えになってみて下さい。
茶入開闢の伝説では「道元禅師」等と入宋した「加藤四郎左衛門景正、世にいう藤四郎」が「唐物茶入」と「陶土、釉薬」を持ち帰ったのが始めとされています。
 しかし一説にはこの時藤四郎が持ち帰った茶入を「漢作唐物」持ち帰った土で瀬戸で焼いたものを単に「唐物」とするという説やら「加藤唐九郎」先生に依れば藤四郎などは伝説の人間、架空のことだとする意見やら諸説があり、はっきりしません。殊に「加藤先生」などは「志野焼」の窯場は「瀬戸」でなく「美濃」であったということを自らの発掘、研究に依って見出したといったことで当時未発掘の「唐物茶入」に関しては否定的にならざるを得ないのでは、とは思いますが。
しかし一説にはこの時藤四郎が持ち帰った茶入を「漢作唐物」持ち帰った土で瀬戸で焼いたものを単に「唐物」とするという説やら「加藤唐九郎」先生に依れば藤四郎などは伝説の人間、架空のことだとする意見やら諸説があり、はっきりしません。殊に「加藤先生」などは「志野焼」の窯場は「瀬戸」でなく「美濃」であったということを自らの発掘、研究に依って見出したといったことで当時未発掘の「唐物茶入」に関しては否定的にならざるを得ないのでは、とは思いますが。
いずれにしても未だこの良く分からない「唐物茶入」という物のがなければ「唐物点という点前」も存在しないという事になる訳で「茶道」それ自体の否定にもなりかねない一大事なので、こんな風に書くと「唐物否定」と言うわけではありませんが、一応これを認めて点前を始めることになります。しかし、未だにはっきりした証明がなされていないにも関わらず、「どうして」一体「誰」が「この茶入は唐物である。」と認め始めその証明を何ゆえに「信憑性」があると認めてきたのでしょうか。
茶道具の「手分け(道具分類の事を茶道ではこう呼ぶ)」の中に「大名物」「名物」「中興名物」といったものがあるのをご存じのことだろうと思います。
「大名物」は利休以前、ほとんどが「東山御物」と呼ばれる足利義政ごろの道具であり盛んに「対明貿易」をしていた時代ですので比較的はっきりと「唐物」と定義できましょう。この時代に同朋衆らによって編まれた書物、「君台観左右帳記」などには使用されていた道具のリストが整っています。
ところが「名物」となると時代も下がり、たとえ「唐物」であろうと市井に埋もれていたほどの「道具」が後に、例えば「利休」の「目利(めきき)」により「唐物」とされ見いだされた物が多いはずです。仮りに利休の鑑定眼を信じるとしても、その「利休による証明なし」にどうやって「唐物」であるかを判断することが一般人に可能でありましょうか。
ま してや数も多く時代も下がる「中興名物」に至ってはたとえ遠州が見いだしたとして、なにをかいわんやでありましょう。また「中興名物」の多くが唐物全盛時代には省みられることの無かった、瀬戸茶入をはじめとする「和物茶入」の方が多く取り入れられています。
してや数も多く時代も下がる「中興名物」に至ってはたとえ遠州が見いだしたとして、なにをかいわんやでありましょう。また「中興名物」の多くが唐物全盛時代には省みられることの無かった、瀬戸茶入をはじめとする「和物茶入」の方が多く取り入れられています。
その他の名物に「八幡名物」「千家名物」等があります。
名物の手分け等に伴い和物である瀬戸なども事細かに分類されて行きます。利休を始め織部、遠州、など自らの指導で築いた新しい窯で好みの茶入などを焼かせて行くようになります。
これらもまたその一部は名物として取上げられるようにまでなっていくのです。その中には遠州自信が指導した遠州七窯など当時としての「今物」まで含まれてきます。
しかし、江戸の後期に至りこれらは「松平不昧」の「雲州蔵帳」により、それぞれは完璧な手分けとして世に流布され「高橋箒庵」による「大正名器鑑」に繋がり、その地位を不動のものとするのです。
とりわけ瀬戸茶入の手分けはことのほか喧しく言われ世に伝わっています。
おおざっぱな分け方をしますが、「瀬戸茶入」の手分けを第一とし、初代藤四郎の作とされる物を「藤四郎」または「古瀬戸」隠居後の作とされるのがその法名と言われる「春慶」二代目とされるのが「真中古」その次が「金華山」「破風」と続き大まかな分け方としての「古瀬戸」はここまでそれ以降を「後窯」とします。「後窯」にはそれぞれ、指導したとされる人物の名を取り「利休」「織部」「宗伯」「鳴海」「正意」があり、「瀬戸十作」「瀬戸六作」と呼ばれる作家が活躍したともされています。
 他に「国焼」として「高取」「薩摩」「上野」「唐津」「膳所」「志戸呂」等や「六古窯」の「丹波」「伊賀」「備前」「信楽」等が挙げられ「仁清」にも名品があります。
他に「国焼」として「高取」「薩摩」「上野」「唐津」「膳所」「志戸呂」等や「六古窯」の「丹波」「伊賀」「備前」「信楽」等が挙げられ「仁清」にも名品があります。
多くの茶入がそれぞれ所持した人々が、「仕覆」を添え「蓋」を替え「挽屋」を造り「箱」を重ね、「盆」を添わせ大切にされながらも時に災いに逢い、粉砕をされても焼け跡からそれを取り出し「修復」し再び世に伝え人から人へ伝えられてきた重要な道具なのでした。その物語、その歴史、即ち「故事来歴」こそが茶道具の命なのです。長々と書きましたが要するにそれぐらい茶入に限らず茶道具とは時代と伝来を重要視され今日に至っています。それが「箱書」であり「添え状」なのです。かつて十五年ほど前、ロンドンの大英博物館にまだちゃんとした日本室がない頃、「仕覆」も「蓋」も「箱」もない「瀬戸茶入」ただの焼き物としての価値のみを表現するのか、三つが並べられていたのを見る機会がありました、その時このような状態で果たして「茶入の意味合い」を伝えることが出来るのかと思ったことがあります。同様のことを「熊倉功夫先生」がボストン美術館で感じられたことがあると語られておられました。
お茶道具の見方は純粋な美術品の見方とは異なり、伝わり形を重視し付属品の「仕立て」がそれを表す物の一つです。茶入は茶道具の中では「重い道具」でありより「古さ」「伝わりの良さ」が必要な物と考えて下さい。
そこには、茶道具独特の「箱書文化」とも呼んでいい「伝来証明文化」ともいえる物があるかと思います。
 近年、茶会と云えば「薄茶席」を指すぐらいに「濃茶」を設ける事が少なくなってる中、茶入の重要性が失われたかのように扱われていますが原点に帰りその茶室での位置を再確認したいものです。
近年、茶会と云えば「薄茶席」を指すぐらいに「濃茶」を設ける事が少なくなってる中、茶入の重要性が失われたかのように扱われていますが原点に帰りその茶室での位置を再確認したいものです。
私が言いたいのはこうして数百年の伝統を維持してきた道具は何故を持って認められ伝承してきたか、ということを考えて欲しいのであります。時代的にもはっきりした伝承の有る「東山御物」はともかく、その他の多くは「茶聖利休」があるいは「遠州」が認めたものという事によってその茶入は四百年人々によって伝わってきた、という事実です。先ほど述べてきた名物の茶入などやそれに準ずるもの等は、お手に入れられなくとも美術館、博物館で是非是非ご覧になって頂きたいと存じます。道具を知る早道は出来るだけ多く「本物」に触れると云う事以外ないかと思います。例えば漢作唐物の肩衝が如何に大きいか、文琳とは出回っている文琳と如何に異なるのか、和物と唐物または漢作と如何に違った風情があるのか。伝来の茶入とは如何なる風格を持ったものなのか。よしんば手に取る事の出来る機会が有れば、どの様な重みがあるのか、附属品はどの様に添えられているのか。よくよくご覧になって頂きたいものです。ただ現実にそれらの物を手に入れる事は不可能と云っても過言ではないほど流通していません。また大変高価でもありますが何にても本物を知ると云う事が大切です。
しかし、茶事にお使いになるような茶入を求めるにはむしろ現代の方が先ほど述べた薄茶優先の時代背景から比較的容易なのではないでしょうか。伝来の確りした茶入であっても一国と取り替えると言われた時代の比ではありませんし、そこそこの時代の物であれば新しい作家物の棗を求めるぐらいで手に入れる事も可能です。
但し何時の世もこの業界に付き物なのは残念ながら贋作です、信用の於ける確りしたお店でよく説明を受けお求めになるほうがよいでしょう。お家元の箱書きといえども新作が化けている場合も有りますし、箱書き自体も気を付けなければならない時代ですので悪しからず、くれぐれもご注意下さい。良い茶入を見つけたらご自分なりのお仕覆などを選び使いやすくされるのが良いでしょう。古い裂など痛みが激しく使えないものも有ります。使ってこそ道具は生きてきますので是非お使いになりやすいようになさることをお勧めします。
茶入の「銘」も重要な要素になります。遠く室町時代から所持者の名前などから取られた銘がありましたが、遠州がその名物選定にあたり古今の和歌集ことに「古今和歌集」「新古今和歌集」などから「歌銘」を取り入れた事により文学的要素が大いに取り入れられることになります。
現実としてご自分のお茶事に使用したり、茶会に用いる茶入などはどうしたらよいのでしょうか。
それには幾つかの方法が有るかと思います。まず、「唐物茶入」の入手は出来なくはありませんが、使い道が限定されますので最初に持つことはお勧めできません。普通使用しやすい茶入を求める方法としては和物、取り分け「歴史」のある物が理想だという事を念頭に置いて下さい。
和物の始めである瀬戸の手分けを重々理解した上で名物は別にして「後窯」の「利休」「織部」「宗伯」「鳴海」「正意」や「瀬戸十作」「瀬戸六作」なら理想ですが、たとえ近世の物だろうと、或は現代作家であろうとまずは、第一に「瀬戸茶入」を求めるのはお勧めできます。
但し、現代作家の中では目立った人がいないのですが。
次ぎにお勧めできるのは遠州の指導した窯である「遠州七窯(高取焼、膳所焼、上野焼、志土呂焼、朝日焼、古曾部焼、赤膚焼ぐらいの順で)」の物を探す事です。これらの窯は先に述べたように茶入の中興名物が多く出ています。遠州七窯の中では現代作家でもうまい作家も多くいますし、やや古い手も見つけだすことは容易です。
他に「国焼」として「薩摩」「唐津」等や「六古窯」の「丹波」「伊賀」「備前」「信楽」等を視野に入れることがあっても良いでしょう。
しかし「国焼」として考えられる焼き物の中でも、あえて茶入に用いずとも「茶碗」「花入」「水指」等他の茶道具に多く用いられる「六古窯」の「伊賀」「備前」「信楽」等や朝日焼、古曾部焼、赤膚焼等は求める順位としては後回しにする方が良いと思います。
同じ理由で「萩焼」や「楽焼」の物、唐津でも「絵唐津」、薩摩でも「白薩摩」「献上薩摩(色絵の物)」などはよほどでないと不必要ですし、歴史的に存在しない「高麗物」の茶入などは「物好き」の域かも知れません。
稀に「島物」と呼ばれる「南蛮」の手などの茶入が散見する事が出来、形が端正なら時代も風格も和物に比肩できる物でしょう。
島物の中でも「四滴茶入」にふくまれる形の物や「呉須」や「染付」「安南」「和蘭」「色絵」は濃茶器の範疇ではなく、「替茶器」「薄茶器」として用いるべきでしょう。
これとは別にお稽古に使うための茶入を求める方法としては「本歌」をよおっく理解した上で「写」の茶入(これも同様に、たとえ近世の物だろうと、或は現代作家であろうと)を求める事もお勧めします。
避けなくてはいけないのは何焼とか何々の窯と表現していいか分からないような作品や、見立てに当たるものなどです。
お稽古にはそのお稽古に相応しいものから揃えるのが一番です。添える「仕覆」にしても本歌の茶入に添ったものや「名物裂」のはっきりした名称のある写しの物を選ぶべきかと思います。着物もその中身の品格を表すものになるからです。
「蓋」も出来るだけ「象牙」の物をお薦めします。永年の間に変色して風格が加わるのが特徴です。
土物の茶入など使い終わったら必ず湯通しして洗いお茶を残さないようにしましょう。古いお茶が残っていてはせっかくのお濃茶も台無しです。中に釉ある茶入は日頃ティッシュで拭く程度で充分ですが数箇月使ったら良く搾った付近で丁寧に外を拭いて下さい。綺麗になる上、思いのほか茶入のすべりが良くなります。
形状も唐物の手分けを基準に「小壷」「肩衝」「雑」に大きく分けます。
「小壷」には「茄子」「文琳」「丸壷」「瓢箪」等があります。「肩衝」「大肩衝」「小肩衝」に大別されます。
「小壷」「肩衝」に含まれない物を「雑」とし様々な形状があることは知られていますが、「大海」「塁座(るいざ)」「鮟鱇」などがこれらに含まれます。
一般には「肩衝」が使いやすいようですが、唐物では「小壷」を上位に据え取り分け「茄子」ついで「文琳」に重きを置きます。和物であっても「小壷」もあり、肩衝茶入と同様にお使いになれます。また「小壷」「唐物」の蓋は「瓶子蓋」の物と勘違いをされている方も多いようですが、実際の唐物でも「瓶子蓋」はほとんど見受けません。お稽古での扱いを習うため使用したのが一般化し、「小壷には瓶子蓋」となってしまった最近の事です。
時代の物には「雑」に含まれる物が多く存在しますが、和物であれば薄茶器に準ずる物となり、濃茶で用いる場合は「侘びた風情」で用いると良いでしょう。