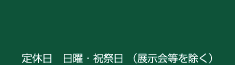(茶杓)
「竹を削って作り茶の粉を掬って茶碗へ入れるだけの匙」が茶杓に対する茶の湯をしていない人の感想です。もっと悪く言う人に掛かれば「耳掻きの親分」なのですが、茶の湯に関係ない人、または茶の湯の浅い人にとっては、これがまた「数百万円」あるいはもっとするものがある!と聞くと引っくり返るほどびっくり(まるで某宗教の壷のような物かと)開いた口がふさがらないほど、あきれ返るのですが、果たして「茶杓の価値」とは一体何なのでしょう。まずは歴史から見ていきましょう。
 「茶杓の歴史」
「茶杓の歴史」
「茶経」を筆頭とする中国茶の中での抹茶のための匙ではないので、金属製のものや貝殻を使った「計量スプーン」を目的としたものだったようです。わが国に招来した唐物の茶杓の中にも金属製の物も入ってきたようですが遠州が「水屋用」としるし「本席」には一度も使用しなかったことは有名な話です。わが国では「象牙」を主に使用し、日本での創作のように思われがちな「竹の茶杓」にも「唐物」がありました。象牙の茶杓はどこで削られても唐物の扱いをします。「象牙」自体が輸入品であるからにほかありません。室町時代の茶杓は「茶杓師」の手になるものがほとんどといって過言ではありません。義政公の茶杓「笹葉」が伝わっていますが今では「真作」としての説得力に欠けるようです。この時代、珠光の門人とも言われる「深見珠徳」節無しの長茶杓を創作し「珠徳形」といわれるようになりました。節を中ほどに持ってきたのは利休からとも言われていたことも有ったようですが勿論それ以前から節を利用したものはありました。
茶杓師に紹鴎時代では「羽渕宗印」利休時代には「慶首座(けいしゅそ)」利休から織部にかけては「甫竹」が著名です。利休以降は茶杓の作は「茶人」へと移り「茶杓師」の影は極めて薄くなり、やがて茶人の「下削り」を行うようになります。「黒田正玄」などはその代表となります。勿論茶人自ら削った茶杓も多く「人となり」を表す物になります。
「竹の茶杓」は少しばかり手ほどきを受けたなら誰でも作れるものです。古い時代の数奇者や茶人の作よりはるかに上手に綺麗に素晴らしく作れる方もこの文章を読んでいらっしゃる方の中にいらっしゃることと思います。
また「職人」としてもっと素晴らしい茶杓を削られる方もおいででしょう。しかし、それらの技術的には素晴らしい茶杓の価値は限りなく「ゼロ」に等しいのです。即ちどこまでいっても「水屋用」であり「稽古用」のものです。あまつさえ、自ら「銘」を付けて「筒書」や「箱書」をし茶会に使うなどもってのほかです。これは「私に(作者に)頭を下げよ、尊敬しろ」と暗にいっているのも同じ事で客に対し甚だ不敬な事です。
なぜ、「ゼロ」かといいますと「茶杓」は「掛物」や「竹の花入」と同じでその技術や熟練ではなく「茶人としての技量、人格、禅者としての悟りの深さ」を価値観の基準として表現されるものなのです。即ち「お人」なのです。現代、茶杓の下削りの作者として知られる「千家十職」の一人「黒田正玄」氏の茶杓であって、どんなに立派でも決して、そのまま使用したりすることはありません。必ず「御家元」の「仕上」と「銘」が付いて初めて使える「茶杓」となるのです。お家元などがが「自作」と署名されるのはそのためです。
茶杓にサイン即ち「落款」や「署名(花押)」のある物は極わずかしかなく、入れ物である「筒」や「箱」に記してあるのみです。もともとは利休時代に茶杓の保存や進呈用に竹筒に栓をして、封印とサイン(花押)また、あて先を「何々様まいる」などと記したりした物だったようです。それに箱書きが加わり現在のような形になっていきます。
かてて加えて「伝わり」も大事な要素です。「茶入」の項でもお話ししましたが、何所で誰が何時焼いたかもしれない、さして綺麗でもない(?)壷が一国と取り替えられるほどの価値を持ち得たのは、茶入そのものが備えた「品性」とともに「伝わり」即ち「伝来」「故事来歴」に価値があったからに他なりません。同様に「茶杓」にもまず「誰」が削ったか(誰にやったか)「銘」の文学的、宗教的重要性を兼ね備えた表現、すべてが「茶の湯的」といってよいでしょう。
 茶の湯のそういった文化に批判的な人は(茶の湯をやっている人を含め)「茶杓本体」のみを論じようと躍起になり「中身が入れ替わってしまえば判らなくなる」とか「筒や箱だけ一人歩きする」などといった批判をしたりします。長い茶の湯の歴史の中には確かにそういったこともあったことは事実ですが、高度な茶人たちの茶事、茶会での会話の中には、拝見に出した茶杓の作者を隠し客に推理させる、などと言ったことも行われており、杓の特徴から作者や制作年代などを言い当てることも容易なのです。「そんなことはなかなか出来ない」と思われる向きもおありかとは思いますが、例えば裏千家の「淡々斎」「圓能斎」「玄々斎」の茶杓を言い当てるのはさして難しいことではないのではないですか?特徴をつかみさえすれば皆さんにもお出来になることです。
茶の湯のそういった文化に批判的な人は(茶の湯をやっている人を含め)「茶杓本体」のみを論じようと躍起になり「中身が入れ替わってしまえば判らなくなる」とか「筒や箱だけ一人歩きする」などといった批判をしたりします。長い茶の湯の歴史の中には確かにそういったこともあったことは事実ですが、高度な茶人たちの茶事、茶会での会話の中には、拝見に出した茶杓の作者を隠し客に推理させる、などと言ったことも行われており、杓の特徴から作者や制作年代などを言い当てることも容易なのです。「そんなことはなかなか出来ない」と思われる向きもおありかとは思いますが、例えば裏千家の「淡々斎」「圓能斎」「玄々斎」の茶杓を言い当てるのはさして難しいことではないのではないですか?特徴をつかみさえすれば皆さんにもお出来になることです。
茶杓を論ずるとき多くの場合「茶杓の作者と茶杓」という観点と「茶杓の真行草の格付けと使用方法」といった少し異なる観点で論じなければなりません。
前述の「象牙の茶杓」は「利休形」「珠徳形」「利休形に真塗りしたもの」のみが「真」の扱いをします。
唐物を原型とするという理由からでしょう「節無茶杓(長茶杓)」も「真」の扱いにします。
「行」にあたる茶杓は「元節」茶杓です。
「中節」の茶杓は「草の茶杓」という扱いですが「伝物」を除くすべての点前に使用する標準的なものとなります。江戸の初期までのものは保護のため「拭き漆」施してありますがそれ以外の「蒔絵」などの「塗りの茶杓」は「茶人」の手から「職人」の手に委ねられた物で「草の草」と言って良いでしょう。同様に「鼈甲」「その他の木製」も同様です。
象牙茶杓の中でも「薬匙」からの転用である「芋の子」茶杓や細工の入った「牙茶杓」は「草の茶杓」というより「茶箱用」として楽しむ意外には使用しません。たとえ「真の茶杓」より古いものであっても、「草の草」以上に番外的な扱いとなります。
 「侘茶の道具としての茶杓(花入、蓋置) 木地の茶道具(水指、建水、等)」
「侘茶の道具としての茶杓(花入、蓋置) 木地の茶道具(水指、建水、等)」
竹で出来た「茶杓」「花入」「蓋置」は掛け軸と同様に「万人」とはいいませんが「尊敬に値する人の作」であることが必要なのです。わきまえた「茶人」なら決して手を出さないものと心得ておかれるべきでしょう。
「青竹の蓋置」と「木地曲の建水」の使い始めのエピソードには今に繋がる侘び茶の原点があります。
侘び茶の道具として珠光は青竹の蓋置を木地曲建水に仕組んで使用し、そのあと蓋置を建水の水に浸し持って帰り「再びこれらを使用しない」印として扱ったとのことです。「木地物の茶道具」の原則は「使いきり」と覚えていてください。侘び茶の道具というのは非常に厳しいものです。一つ間違えると「しぼたらしい」「貧乏臭い」物になりかねず、それと取り合わせる青竹や木地物の茶道具はことさら「使い切り」を求められます。
茶筅
点前道具の一種。茶を点てる竹製の具。等といわれてもしらけるほど身近な道具の一つです。茶筌とも書く事があります。
宋代の茶書『大観茶諭(だいかんちゃろん)』に「筅」とあり、そのつくり方や点茶法が見え、また「琴棋(きんき)書画図」などにも茶筅が描かれており、宋代に発達したのがわかります。
 これがわが国に伝来、室町時代の初頭には販売・贈答が知られ、『遊学往来(ゆがくおうらい)』に「紫竹茶筅」が見えます。
これがわが国に伝来、室町時代の初頭には販売・贈答が知られ、『遊学往来(ゆがくおうらい)』に「紫竹茶筅」が見えます。
次いで戦国時代は奈良茶筅が名品とされ、加賀・尾張・山城幡枝の名が『鳥鼠集(うそしゅう)』にあり、改良も進みました。
この奈良茶筅の伝流として、大相国西北境の鷹山(奈良県生駒市高山)が製造をはじめ、利休時代以降は独占的製産を誇り、また江戸幕府から茶筅業が免許され、茶筅師として士分の格に遇せられました。
すでに、白竹・紫竹・黒竹・油竹(煤竹)が利用され、竹の材種や形姿に各流儀が発注し、表千家では煤竹、裏千家・藪内家・遠州流などでは白竹、武者小路千家では紫竹を原則とし、真・数穂・筑穂・筒茶碗用の五分長、茶箱用の小寸など品種も数十種を数え、今も独占的盛業を続けています。