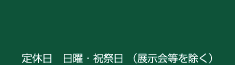今一般に「茶の湯」と呼ばれ「茶道」と称される物は、何れの流儀に属していても、必ず「侘茶」を精神的根幹と考えているのではないでしょうか。
しかしながら、侘茶とは何かを具体的に考えたことはありますか、と問われたら果たしてどうでしょう。
「茶道史」の中でもお話をしましたが、村田珠光以来、歴史の主流は侘茶の系統のみが語られているのはご存じのことかと存じます。
「古市播磨(澄胤)」宛ての「村田珠光」の文章に始まり、武野紹鴎、千利休と侘茶の発展系列は語られますが、侘茶とは何かを語り出すと「精神論」的領域に入り込みやすく分かったようで分からなくなるのではないでしょうか。
「侘び」や「侘びしい」という言葉を辞書で引くと「貧しく、みすぼらしい」世界が広がっているかの様なイメージがあることも、「侘茶」の解釈を些か狂わせている元凶なのかもしれません。
それでは逆に「侘茶の対極にある茶の湯」は何か、と考えてみてはいかがでしょうか。
そういった「茶の湯」とは皆さんの中にはどういったイメージがあるのでしょうか。曰く「派手なお茶」「豪華なお茶」「お金持ちが高い道具でするお茶」などと思っていらっしゃる方、結構いらっしゃいます。
果たして皆さんのイメージと合った物なのでしょうか。
「派手なお茶」のイメージとは例えば「仁清写の色絵陶器」や「交趾物」塗り物であれば「蒔絵」を施した茶道具を使った、「美々しい色鮮やかな世界」或いは「棚物」などの造形が賑やかな世界を指すことがありませんか。
しかしながら私の結論から言いますとそれは、いわゆる「台子書院の茶」になると思います。
それでは、室町時代行われていた「台子書院の茶」とはどんな取り合わせで行われたのでしょうか。
その代表として、現代に伝わる「真台子」の点前に使われる道具組を参考に考えていってみましょう。このお点前自体は六百年の変遷を経て些か当時のものと異なっているかも知れませんが、そこで使用する道具に関しては考察するに大きな違いは無いかと思います。
第一に掛け物は「唐絵」と呼ばれる絵画ですが、色彩の押さえられたモノトーンに近い世界で描かれる事が多く、色彩の派手さはありません。花入も「唐銅」ないし「青磁」でトーンは落ち着いた色合いです。
「真台子」の名称ともなった台子はその名の通り「真塗」黒一色で蒔絵など施されることはなかったようです。
中に入る「風炉釜」「皆具」も「鉄」や「唐銅」で出来ており色合い、形状もいたってシンプルと言っても良いでしょう。
茶碗は最も華やかな「窯変天目」にしても漆黒の中に青い斑紋が点在する程度、いたって地味、「天目台」も「尼崎台」を代表として黒塗りされていますし、茶碗、台共に「覆輪」が懸かっているのも器物を保護するために施されているに過ぎず装飾のためではありません。
茶入にしてもご存じの通り地味な色合いですし、それぞれに添った「仕覆」も比較的落ち着いた柄のものを用いているようで、全体を取りわせてみても色調は穏やかなものとなっています。
ですから、皆さんの想像する、華やかで色鮮やかな茶湯はむしろ、侘茶の完成以後、一種の侘茶によって造られたものである、とも言えるのです。
「豪華なお茶」「お金持ちが高い道具でするお茶」などはどうでしょう。確かに室町時代であっても一時代前の唐物が多く使われ「豪華」な雰囲気は当然あったと想像できますし、「お金持ち」に至っては「とてつもなくお金持ち」、と考えた方がよいでしょう。例えば地方都市の年間予算を自由に使えるぐらいの金持ち、ぐらいの感覚、で思考していただきたいと思います。
ですから、中途半端な使いようでなかった、それがやがて信長の「茶湯政道」にも発展していくわけです。
「和敬清寂」
侘茶の精神を表す言葉で、茶を志す人で知らない人がない言葉に「和敬清寂」があります。
「和」
茶湯は「数寄」とも呼ばれることがあります。「物数寄=物好き」から来た言葉で、本来は物=茶道具に執着することを指したのでしょう。そうすると、先に述べたように大変な事態になり、身を持ち崩しかねない。その様子を千宗屋氏は「死屍累々」と表現していて思わず、自虐的に笑ってしまいました。
「絶妙な趣向」と見事な「道具の取り合わせ」をされた「茶事」に遭遇すると、それが例え「会記」の中だけだとしてもとても興奮を覚えたりするのは筆者のみではないと思います。ましてや実際に招かれ客となった席であれば、その感動たるやいかばかりのものでしょう。茶をやっている者としてはまた、いつの日にかそんな、客人に感動を与えられる席作りが出来たなら、と考えもします。
興奮や、感動を与える席というのは「なぜ」そうなるのでしょう。亭主の取り合わせという、微妙な「和」がそこに感じられるからなのではないでしょうか。
「敬」
この「敬」はどういう意味ですか、と聞くと皆さんはおそらく「お互いを尊敬し合うこと」とおっしゃいませんか。お互いの中には「自分」が含まれているのですから、「私のするお茶なんて」「どうせ私がすることだから」という気持ちは、ご自分を尊敬なさっていない方がおっしゃる言葉だと思います。ご自分がまず尊敬できなければ、人を尊敬することが出来ません。「尊敬する人」をお招きするのに精一杯の努力を惜しむ方はいないと思います。がしかし、前述の「私なんか茶人」の実に多いこと。これは客おも尊敬していない姿で「和敬清寂」からはほど遠い世界です。
利休の言葉にいわく「茶の湯といへるは、湯を沸かして、心をたぎれ、たぎれ。」心が滾る思いが大切「たぎれ、たぎれ」と念じつつ。
「清」
侘茶の中には前述の村田珠光が台子を真塗から「竹柱、桐木地の竹台子」を好み、利休が木地の棚など多く好んだ所から、「侘茶は木地物」と思いこんでいる向きもありますが、一概にこれも言えません。なぜならたとえ木地だからといっても、台子や、棚物は「侘びの究極の空間、小間」では使えないことからでも自明の理です。
「木地で出来た物」とは日本人にとって、どういった物なのでしょうか。日本の文化の根幹をなす、神道、社建築の代表とも言える「伊勢神宮」では二十年で「遷宮」をし、新しいお社に遷す、という事をします。「神は木地の新しい社」にお住まいするという事を表します。
翻って我々の日常生活を考えても、一時、海外からやり玉に上がり、最近ではだいぶん静かにはなった「割り箸の文化」があります。われわれ日本人の感覚として、たとえ仮定の話としても、皆さんはたとえ綺麗とはいえ「洗った割り箸」をお使いになれますか。大概の方はお使いになるのも、人にお出しになる事もされないと思いますがいかがでしょうか。
神代の太古からの日本人の感覚の中に「木地物」は清浄無垢なもので一度使ったら使わない物としています。それが日本人の清潔感なのです。
「侘茶」の感覚としても木地は確かに侘びに近い物と考えられますが、本来「木地、青竹」の物は清浄であるが故に「使い捨て」の物なのです。
「茶道具」で言えば、「黒文字の箸、楊枝」は勿論、「懐紙」「使帛紗」「茶筅」「茶巾」「柄杓」「青竹の蓋置」「灰吹」「木地の水指(曲、釣瓶など)」「木地曲建水」、懐石で言えば「八寸」「箸類」は当然使い切りとなります。
「茶室、露地」ではその都度とはいきませんが「茶人の正月」=「開炉」や「口切」の折りには「露地の筧の竹」「竹の垣根」「茶室の樋」「炉壇の土の塗替」「畳」「腰張」「障子紙」「襖の唐紙」の果てまで替えるのが「侘」なのです。また客への心入れとして、本来なら亭主の手になる「懐石料理」「菓子」足で活けるとも言われる「花」名水を探した「水」自ら切った「炭」手入れのよく行き届いた「灰」。
そういった物が整えつつ「心血を注いだ茶道具」を集め茶湯を行うのが「侘茶」なのではないでしょうか。それが「山上宗二」言うところの「胸の覚悟」なのだと重います。ですから決して「貧しく、みすぼらしい」世界ではないのです。
「寂」
近年は便宜性を優先するせいか、電熱器の発達でホテル等でのお茶会のみならず、日頃のお稽古まで火を使わない方が増えているようです。先に述べました「侘茶」の観点からもおかしな事ではないかと思います。
南方録の冒頭に「薪を取り湯を沸かし」とある事も皆さん周智の事ですし、利休の言葉として盛んに「湯相」「火相」を事細かに述べているのは「茶の湯」という言葉が示す通り、湯を沸かしその加減を調節するという事がもてなしの第一と考えたからではないかと思います。釜の煮え音を「松風」と称する事はご存知かと思いますがその他にも「茶経」以来、各種の表現で煮え音、沸き具合等を表わした表現があります。それは客をもてなす心がけの最も重要な部位をしめるのですから、疎かにしてはいけないからだと考えます。これを単に電熱器のスイッチのオンオフで済ましてよい事ではないと思います。
筆者などは師匠に未だに灰や炭の選び方等よく怒られます。しかし電熱器は使いませんし、良いお茶を目指す茶人としては「炭手前」を稽古の時にも必ず行います。
(炭)
茶の湯で使われる椚炭の代表として有名なのは関西の「池田炭」です。その切り口がきれいに放射状になっているところから「菊炭」ともいわれています。これに対して関東で焼かれて有名な物はその集積地ともいわれる地名からか「サクラ(佐倉)炭」といいます。「菊に対して桜」の洒落でしょうか。何れも「櫟」の若木を用いて造られます。茶の湯ではこれらクヌギ材の炭を最上とし、次いでナラ材の物が用いられます。
「道具炭」とも呼ばれ流儀により決まった寸法に切りそろえ水洗いして使用します。切ったままの炭は切り口に炭の粉がついており、そのまま火を付けるとパチパチと火が跳ねてしまうので必ず洗い流します。切った寸法、太さなどで様々な名称があります。別に「枝炭」はツツジの枝を焼いた物とされ、黒いまま使う流儀と「御粉」で白くして使用する流儀があります。
炭の名称として有名な「備長炭」は堅炭の代表で、炭の傑作といわれますが元々は鉄の精錬や日本刀を鍛えるのに開発された炭で茶の湯では「料理に使用」するのに用います。また「楽焼」を焼成するのにも用いますが、決して「手前」には使用しません。
点前に使う炭の場合「初炭の下火」や「火入の炭」「後炭手前」の具合等、ことさらに気を使うものです。
(灰)
こうして使用した炭が燃えて出来るのが「灰」です。
「茶人は火事になると真っ先に灰を持出した」ともいわれる灰ですが、火事になれば全てが「灰」になってしまうのにと思われなかったでしょうか。
茶の湯で使う灰はきのう、きょう炭から灰になったものではなく「永年茶人が端正込めて手入れ」したものであるからなのです。それが茶人の力量を示すとされ、風炉の時期であれば「灰形」、炉の時期であれば、炉に蒔く「湿灰」に現れます。それらの手入れの仕方に関しては別の機会に譲るとして、道具の話をするはずなのに、一向に道具の話にならないではないかとおっしゃる方はいらっしゃいませんか。「灰」は「茶人の手掛ける唯一の道具」と云ってもよく、人をもてなすために丹精込めて仕上げるものなのです。「炉」でも「風炉」でも毎年手入れを欠かさず、永年使用してきた灰はその灰を見ただけで頭が下がるものです。
時の移ろいの無情を感じるために、利休が当時、白炭といわれていた軟らか炭である「櫟の炭」を用いられたと聞いております。やがてそれは燃えて灰になり、消えていくやに思われますが、利休はその灰にも心入れをした。これが無情を感じるとても分かりやすいもの、人生に通ずる悟りの世界なのかも知れません。すなわち「寂」だ、とは言い過ぎかも知れませんが。